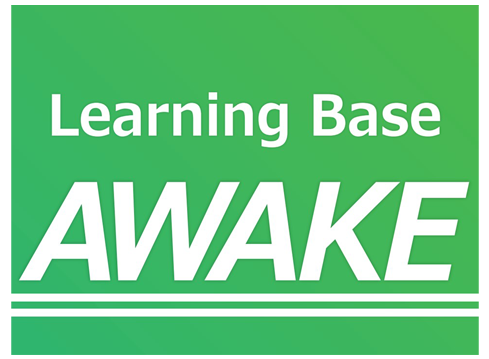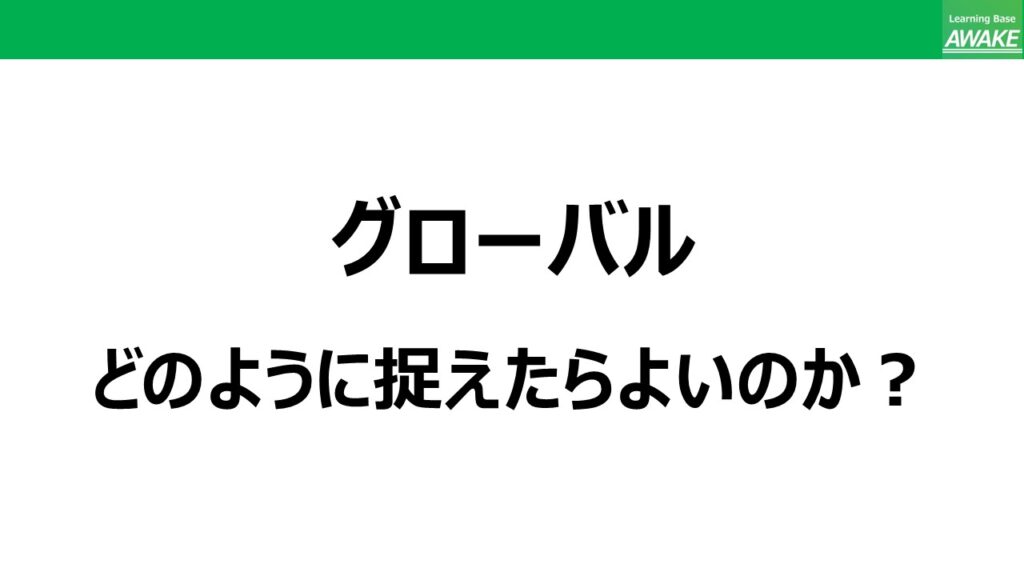
最近、「グローバル」という言葉をいたるところで耳にします。多くの大学で「国際」というワード掲げた学部や学科がやたらと増えた感じを受けています。また、小学校から英語を学ぶようにもなってきました。これらは「グローバル」に対する関心度の高さの表れだと思われます。
このような世の中の流れから、数回にわたって「グローバル」について考えてみたいと思います。
ワードとしての「グローバル」
「グローバル」という言葉を耳にするようになって20年くらいたったでしょうか。私の大学時代や就職したての頃は「インターナショナル」という言葉の方が一般的でした。英英辞典で調べてみると、それぞれの意味は以下のように記載されています。
- “global” : covering or affecting the whole world
- “international” : connected with or involving two or more countries
(from Oxford Learner’s Dictionaries)
「インターナショナル」は2か国あるいは数か国に関すること、「グローバル」は世界全体に関係すること、と解釈することができます。
ここからは、私自身の経験にもとづいて記載させていただきます。
時代による変化
私自身、平成の30年間のほとんどを企業人として過ごしましたが、その間大きな変化がありました。海外とのやり取りを例にとってみましょう。
30年ほど前の海外とのやり取りは直接会って行うことを基本原則としていました。当然、ファクシミリや国際電話を利用しながらスケジュール調整などを行っていましたが、航空券の手配なども旅行代理店に電話連絡して行っていました。その後、部署に一台だったコンピュータが個人に一台ずつ配布されるようになり、Eメールを利用できるようになりました。そこからは、海外の先方とのやり取りの障壁が下がり、個人マターで行うことができるようになりました。当然、航空券の手配なども個人で行うことができ、海外がかなり近くなりました。さらに、テレビ会議システムが導入され、先方と直接会うことなしに会議ができるようになりました。コロナ禍以降は、TeamsやZoomなどにより自宅で手軽に会議ができるようにもなりました。このように海外とのやり取りは、この30年余りで劇的に変化し、迅速かつ簡便になりました。世界がいかに小さくなったかがお分かりいただけるのではないでしょうか。このような海外とのやり取りひとつとっても、インターナショナルからグローバルへの移行は時代の変化は自然な流れであると言えるのではないでしょうか。
日本人にとっての英語
アメリカ駐在中、駐在先の外国人の仲間から「学校で何年英語を学んでいるのか?」と質問を受けたことがあります。「中・高・大の10年」と答えると、「それだけやっていて、なぜ日本人は英語を話せないんだ」と驚かれました。これは日本の本社から出張できた日本人のプレゼンテーション後の一幕でした。
プレゼンテーション自体は英語で行っていましたが、日本人にありがちな台本を読みながらの一方通行のプレゼンテーションでした。会議の場で質問されると、「英語は母国語でないのでちょっと…」と質問に答えずに言い訳する始末。すかさずアメリカ支社の複数メンバーから「英語が母国語でないのは我々も同じだ!」と強く反論されていました。ミーティング後に反論した現地社員に呼び出され、「ビジネスにおいて、英語を話せないことを言い訳にするなんて理解できない!」と強く言われ、同じ日本人として恥ずかしい思いをしました。
アメリカ支社の現地社員の多くはヨーロッパ、インド、中国などから移民した人たち。彼らにとって英語は国籍の異なる者同士が理解し合うためのコミュニケーション・ツールです。しかし異国で生きていく上での生命線ともなり得るものであり、彼らにとって英語を学ぶことは真剣そのものです。彼らの英語に対する意識や認識は、日本人のものとはかなりの違いがあると思います。
このような経験は私が所属していた企業に限ってのことかと思っていました。しかし帰国後に社内の英語教育に携わったときに、他社の人事担当の方々から色々と意見を伺いました。大小の違いこそあれ、各社同じような状況にあり苦慮している、とのことでした。ほとんどの日本人が学校教育の中で英語を学んでいますが、コミュニケーションに活用するレベルにはほど遠いものなのかも知れません。
外国人にとっての英語
社内の英語教育に携わっていた時、仕事の関係で他社の若手外国人と話をする機会がありました。彼らは日本のある大手グローバル企業が海外で開催した就職イベントに参加して採用された方々でした。出身地は1名のアメリカ人を除いて、タイ、マレーシア、シンガポール、香港、韓国とすべてアジア圏。しかし驚くことにほとんどの人がバイリンガル(母国語+英語)ならぬトリリンガル(母国語+英語+日本語)、一人はクアドリンガル(母国語+英語+日本語+中国語)でした。しかも彼らの操る日本語は完璧に近いもの。驚くほどの速度で言語を切り替えながら、日本語と英語を織り交ぜて会話していました。当然のことながら国籍・母国語の異なる者同士のコミュニケーションは英語となり、日本語でうまく説明できなければ英語を駆使するしかありません。彼らのコミュニケーションを通じて、まさに共通言語としての英語を目の当たりにした瞬間でした。
しかも彼らを観ながら強く感じたことは、「グローバル」とは言語ではなく、「ダイバーシティ(多様性)」ということです。ビジネス上において、我々も良く使っていた表現ですが、英語はコミュニケーション・ツールだということです。

しかし多くの日本人にとって「ダイバーシティ」を考えるには環境的にも難しいことです。そのためまずは英語をしっかりと学んで共通言語レベルに引き上げることが大切なのではないでしょうか。
次回以降では、英語をどのように学んだらよいのか?について、少し掘り下げてみたいと思います。