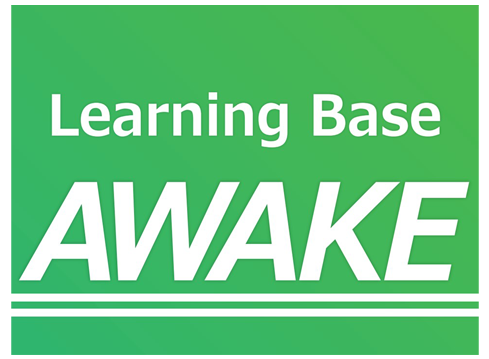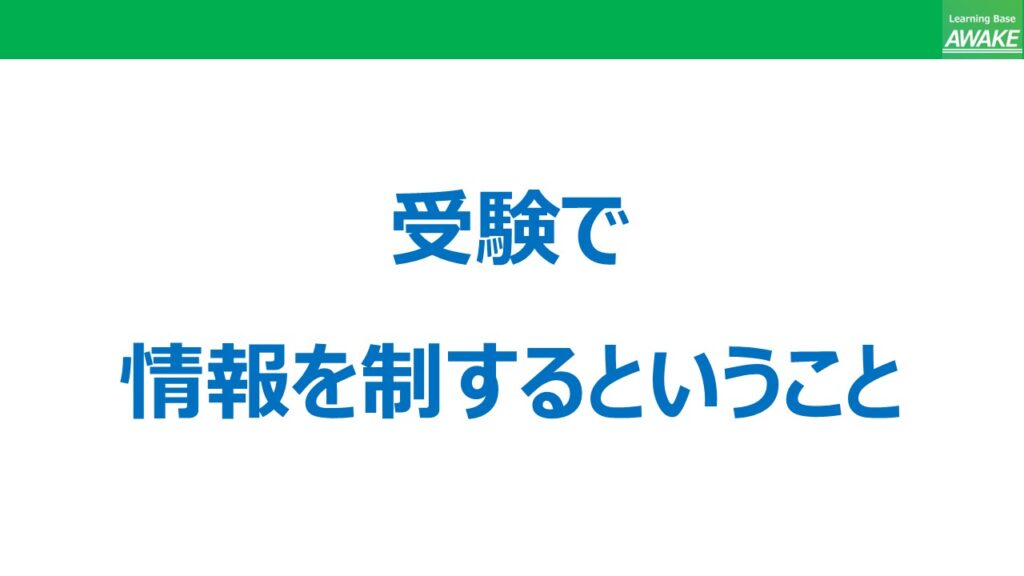
「情報を制する者は戦いを制す」
これは中国古典である『孫子』に由来しているといわれています。今から遥か昔の春秋戦国時代においても戦いを有利に進めるために「情報」の重要性が説かれています。
『孫子』に学ぶ受験必勝法 準備編_豊明×塾×高校生×中学生 – Learning Base AWAKE
このことに倣って、「情報を制する者は受験を制す」ともいわれています。
今回は、「受験においてどのように「情報」を制していけばよいのか?」について少し触れてみたいと思います。
情報の価値
前職では研究・開発における企画部門に所属していたことがあります。企画部門では自らデータを生み出すようなことはありませんが、専門部署から得られた多岐にわたる情報を集約・分析することで研究・開発における戦略を立案し、実際に実行部隊を率いることを主な業務としていました。その時の経験からいえることは「情報は価値あるもの」であるということです。
今から10年ほど前までは情報の入手は極めて難しいものでした。「自分の足で稼ぐ」といわれるほど、色々なところで情報収集したりする必要がありました。その後インターネットが発達することにより、これまで入手困難であった情報が次第に容易に入手できるようになりました。現在のデジタル社会ではいとも簡単に入手できるようになったとの印象を持っています。入手が困難であり、手にする人の数が少なければ少ないほど、その情報の価値が高いことは確かだと思います。このような観点からから考えると、現在ではその情報の価値は下がったかのように見えます。しかし情報は単なる記号のようなもので、その価値は活用して初めて生まれます。活用しなければ「宝の持ち腐れ」になりかねません。手にした人が情報をどのように活用するか次第でその価値を何倍にも高めることができるのではないでしょうか。
情報の活用
企画部門に居た頃、情報収集のスペシャリストとも呼べるような同僚がいました。彼の情報源は大学教授からの意見聴取だけに留まらず、専門誌、学会、ニュース、新聞、雑誌、ネットなどなど、様々なものがありました。よくその情報を我々に共有してくれていましたが、その情報の種類は驚くほど様々でした。しかし彼は情報を集めることには秀でていましたが、分析することが苦手でした。フェイクのものなども含まれていたため、我々自身が選別作業をすることもよくありました。このときに学んだことは、情報を正確に読み取り、正しい情報を入手する、ということでした。情報の出所はどこなのか、その情報の裏付けはあるのか、情報が示す意味は何なのか、などを考える必要があります。特に「情報が示す意味は何なのか」は重要だと思います。
ここで「合格点」を例にしてみたいと思います。
各大学が掲示している入試結果には「合格最高点・最低点・平均点」が公表されていることがあります。多くの人は合格最低点に目が行くのではないでしょうか。中学数学で学ぶ「箱ひげ図」を思い浮かべていただければいいと思いますが、合格最高点・最低点はそれぞれその点数を出した合格者一人のデータにすぎません。受験者が何人いたのか(倍率など)によっても左右される可能性があります。例年より受験者数が少ない場合、合格最低点が低くなることがあります。このようなときには平均点も引き下げられる可能性があります。中央値や標準偏差のようなバラツキが公表されていないため、他の年度も含めて経年変化で比較する必要も出てくると思います。
難しいことを述べてしまいましたが、「情報の示す意味」をよく考えてみてください。
諸刃の剣としての情報
情報には正・負の両面があると思います。先に述べたように情報は単なる記号です。手にした人がどのように扱うかでその解釈が大きく変わります。企画部門にいたときの話を例に挙げてみたいと思います。
担当するプロジェクトを進める上で、キーオピニオンリーダー(KOL)と呼ばれる専門家や権威者の存在が重要となるときがあります。このようなときにはKOLを訪問し意見聴取を行います。自分たちが考える方向性にKOLが賛同してくれることを願って意見聴取に伺うのですが、時には反対される場合もあります。そうなると複数のKOLを訪問して意見聴取を行います。3件、4件、5件と行ううちに、2勝3敗などと勝率の話になっていきます。こうなると本末転倒で情報の意味や価値も薄れてしまいます。逆に考えると、賛同してくれるKOLのみから意見聴取をすれば自分たちの方向性を正しいとすることができ、ある意味で情報操作することが可能となってしまいます。つまり情報が諸刃の剣となってしまうということです。
人の性のようなもので、誰でも自分を指示してくれる情報を欲しています。しかし情報を誤認・誤解することでとんでもないことになってしまうこともあります。できる限り視野を広げて情報を収集して分析していただきたいと思います。
情報源(チャンネル)
「情報難民」という言葉があります。GoogleのAIによる概要には、「必要な情報を得る手段が不足していたり、情報リテラシーが低かったりする人々のこと」とされています。これだけインターネットやSNSが普及した社会で生活している中・高生がデジタルネイティブと呼ばれるのも納得できます。我々の世代と比べるとデジタル機器に対する適応能力が抜群であり、さらに情報収集能力にも長けています。しかしなかには情報リテラシーが十分に高くないために、ある意味で「情報難民」のようになってしまっている学生を目にします。このような学生は情報収集する情報源(チャンネル)の数が限られているようで友達からの偏った情報を鵜呑みにしてしまっていることもあります。できる限り様々なチャンネルから情報を入手することで情報の偏りを避けるようにしてみることがよいと思います。
最後に
情報を価値あるものにするかは皆さんがどのように活用するかにかかっています。今はインターネットから簡単に情報が入手できます。羨ましいことにオープンキャンパスもあります。SNSを使って情報を入手することもできるでしょう。情報は様々なチャンネルから入手し、正確に読むことでその価値が高まります。価値ある情報は皆さんの武器にもなり得ます。是非、情報を制して受験を成功に導いてください。