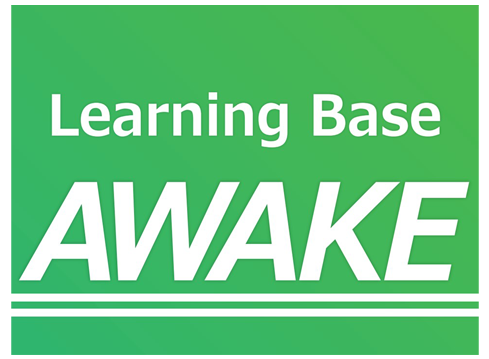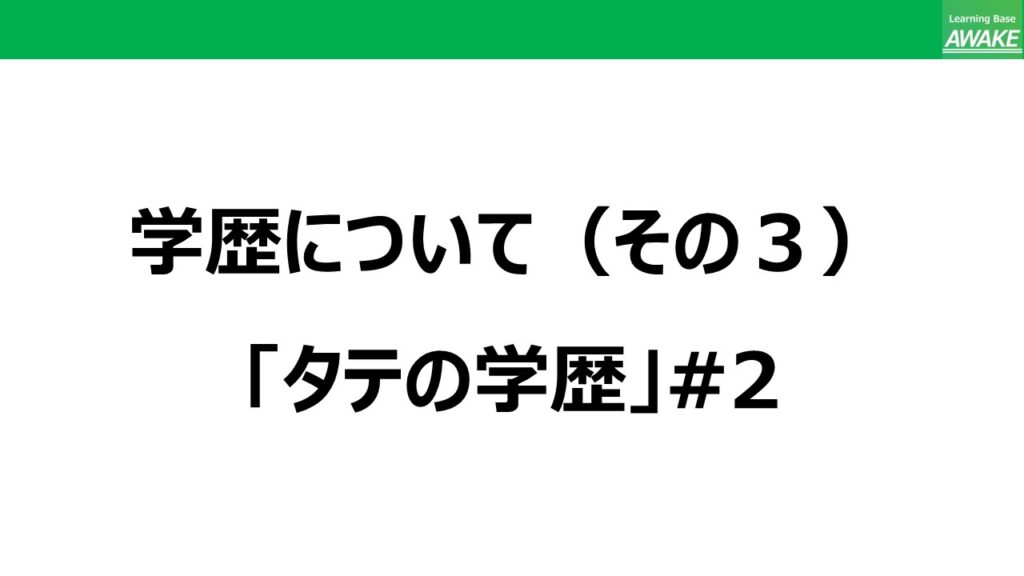
前回のブログでは「タテの学歴」についてご紹介いたしました。グローバル社会では「ヨコの学歴」より「タテの学歴」が重要視される傾向にあり、「グローバル」という言葉がかなり定着してきた日本だからこそ、グローバル目線で学歴を考えるきっかけになっていただければ幸いです。今回は続編として、「タテの学歴」を別の角度から考えてみたいと思います。
研究機関としての大学
大学を学ぶところと思われている方は意外に多いのではないでしょうか。確かに大学では様々なことを学ぶことができ、名立たる先生から専門的講義を受けることができます。一方、大学は研究機関の側面も併せ持っています。どちらかと言えば、研究機関としての側面の方が大学の主体と言えるのではないかと思います。大学に進学すると文系・理系問わず、少なからず研究に携わることになります。研究成果を卒業・修士論文にまとめ、受理されることで学位記が授与されることになります。大学在学中に大きなウエイトを占めるのが研究活動です。また研究から得られた成果や知見が、社会の発展に少なからず貢献することとなります。大学に進学したら、是非研究というものを楽しんでいただきたいと思います。しかし、この研究活動を「タテの学歴」から見てみると少し違う側面が見えてきます。
学士段階での研究活動
大学を卒業すると、晴れて学位記が授与されます。そのためには卒業論文を書く必要がありますが、大学4年生のときに実施した研究をベースに作成することになります。基本的には指導教官から与えられたテーマに即して研究を実施することになります。学生は実際に手を動かす研究の実行面を担当し、通常、得られた結果の考察などは指導教官と一緒に行います。私もそうでしたが、学生は自分が担当して研究ができることが楽しく一生懸命に行います。指導教官のもと、得られた結果をまとめて何とか卒業論文にしていきます。これは時間と労力をかけたかなり大変な作業となります。
研究というものは、一連の結果をまとめ、学術論文に投稿・発表することがとても大切です。研究結果を世の中に公表し、認められる必要があるからです。しかし、大学4年生の1年間だけの研究結果だけではまとまった内容に仕立て上げるには不十分なことが多く、何年かかけて得られた研究結果を指導教官がまとめて論文として発表することがほとんどではないかと思います。つまり、学士の段階では研究に携わることができますが、実行面に特化した活動となります。
修士課程での研究活動
修士課程では状況がかなり変わってきます。指導教官につくことは変わりませんが、テーマを決める際にも関与することができます。当然、得られた結果の考察、その後の研究方針についても主体的に進めることができます。修士課程の期間が2年あることも追い風となり、かなりまとまった結果を得ることができます。運やタイミングなどに左右されることはありますが、学術集会で発表することもできたりします。学士に比べると雲泥の差です。現に私も運よく発表させていただきました。ただ、大学の公聴会のような場と違い、その分野の専門家を大勢前にしての発表でしたので、途中で頭の中が真っ白になる苦い経験となってしまいましたが。
しかし、学術論文に投稿・発表となると時間が十分でないこともあり、かなりハードルが高いのではないでしょうか。修士論文をまとめることがやっとで、学術論文には手が届きませんでした。現に私の同期でも修士課程で学術論文にまとめた人はほとんどいませんでした。つまり、修士課程でも学術論文にまとめるチャンスはあまり多いとは言えないかと思います。
博士課程での研究活動
「博士号」の学位審査では、学術論文への発表・投稿が必須要件となります。多くの場合、1~2報くらいかと思いますが、それでも研究内容をまとめ、世の中に公表することが必要です。学術論文への発表・投稿は、国内の学会誌などであれば日本語で作成することができますが、海外のものであれば当然のことながら英語でまとめる必要があります。論文を投稿すると第三者の専門家複数名がレフェリーとして査読をします。査読とは、投稿された論文の内容が確かなのか、学術誌への掲載にふさわしいかどうかを判断する作業です。つまり、複数の専門家の公正な目によって論文が審査されることになります。論文の内容次第では追加実験を要求されることもありますし、最悪のケースではリジェクトといわれる不採用もあります。このように厳しい審査をパスして論文が発表されることになりますので、もととなる研究の質も同時に問われることになります。
経験して実感したこととしては、論文発表しないと研究は完結したことにならないということ。学士や修士課程でも研究に携わりますが、その分野や世の中に認められる研究となるためにはまだ前段階だと言えます。もし研究に興味があるのであれば、大学院を目指してみることも良いのではないでしょうか。
大学の研究は企業と異なり営利目的の側面が少ないため、基礎研究に力を注いでいます。研究成果が将来何に化けるか分かりませんが、新たなる発見や知見となる可能性を秘めていることもまた事実です。近年のノーベル賞受賞者が口をそろえて基礎研究の重要性を唱えています。なぜなら、日本では基礎研究への投資が低下する傾向にあり、日本の発展も影響を及ぼす可能性があるからです。これからの大学生となる皆さんに、日本の将来のためにも大学で研究に力を注いでいただけると嬉しい限りです。
「タテの学歴」の現状
グローバル社会では「ヨコの学歴」より「タテの学歴」が重要視される傾向にあると述べましたが、日本ではまだまだグローバル社会に逆行した感じになっています。「修士に比べ博士は扱いにくいからね~」という企業の人事関係者からの言を聞いたこともあるくらいです。現状では「修士号」「博士号」が就職などに有利に働くかは疑わしいと思います。しかし、世の中は少しずつ変わってきていることも確かです。前職では社員の博士号取得を奨励し、推進するための制度を整備していましたし、博士号取得者の採用を促進する動きがありました。社会が少しずつ変わってきている証だと思います。
今後の展望
ここで文部科学省が発表している興味深い資料をご紹介いたします。
少し古いものですが、「人口100万人当たりの博士号取得者数」と「一人当たりGDP」を主要国で比較した結果です。
「資料1」
〇 我が国は、人口100万人当たり博士号取得者数が各国と比較して低い。
〇 人口100万人当たり博士号取得者数が多い国は、一人当たりGDPが高い傾向。
講演会などでも耳にしたことがありますが、日本の現状はとてもショッキングです。主要国と比較した際、日本の博士号取得者数の少なさが際立っています。
もう一つは、冒頭から「論文の筆頭著者の約2割を占める博士後期課程学生は、先端研究の現場の重要な担い手であるとともに、次代の科学技術・イノベーションを担う貴重な存在です。」との始められている以下の資料です。
「資料2」
イノベーションを担う貴重な人財として博士号取得者を位置付けているということ、さらにサポート体制充実させていこうという動きと捉えられ、朗報と言えます。
このような資料から、日本も危機感を持ち、海外に追いついていこうとする動きが見えるのではないでしょうか。最近ではグローバル化が進み、「イノベーション待ったなし」の状況になってきています。この流れで進んでいくと、グローバル社会と同様に「タテの学歴」が今以上に重要視されることになっていき、大学における研究活動がさらに見直されていくことにもなっていくのではないでしょうか。今後の展望はかなり明るくなってきているように感じています。
これから大学進学を目指す学生の皆さん、「ヨコの学歴」だけでなく「タテの学歴」も視野に入れてみてはいかがでしょうか。今回のブログがひとつのきっかけにでもなれば嬉しく思います。
関連リンクは以下です。
学歴について(その1)「ヨコの学歴」 vs. 「タテの学歴」豊明×塾×高校生×中学生 – Learning Base AWAKE
学歴について(その2)「タテの学歴」 個人的体験から 豊明×塾×中学生×高校生 – Learning Base AWAKE