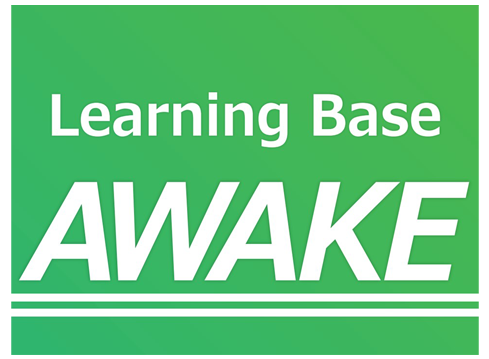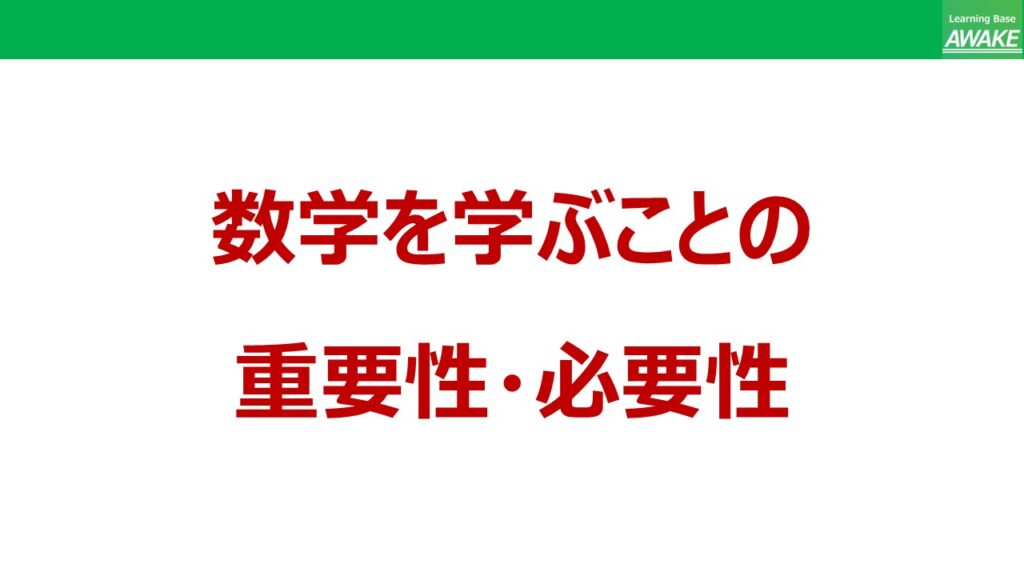
塾生から文理選択の相談をよく受けます。文理選択は将来の方向性に少なからず影響を及ぼしますので、学生にとっては大きな悩みとなっているようです。
それでは実際の文系・理系の選択比率はどのくらいなのでしょうか?世の中の変化にも若干影響を受けたりしますが、10年くらいのスパンで見るとだいたい文系6、理系4くらいの比率で推移しています。私の学生時代を振り返ってみても、理系クラスより文系クラスの方が多かったと記憶しています。さらに世界的に見ても 文系 > 理系 の傾向にあるようです。理系に進んだ者としては理系の比率が低いことは少々残念に思いますが…
ただ文理選択において、とても気になることがあります。私が耳にする範囲との条件付きではありますが、文系を選択した学生からは「数学が苦手・嫌いだから」との理由をよく耳にします。数学を避けて文系に進む学生がいることは昔も今も変わりません。理系でも同様に文系科目が苦手だからという人がいますので何らおかしいことではありません。しかし昨今では「データ社会」と言われるようにデータを重視する世の中に変貌しつつあります。データを解釈する上で重要な教科である数学はこれから益々重要視される方向にあります。
大学受験に目を向けてみましょう。近年では文系学部であっても数学を重視する方向にあります。早稲田大学政経学部では2021年から数学が必修科目となり話題になりました。慶應義塾大学、上智大学などの文系学部でも同様に数学を必修科目とする動きがみられ、この動きは拡大する方向にあります。今のところこのような動きは経済学部を中心にみられているようですが、学部での履修科目に数学を必要とするものが必須化しているとの背景があるようです。また数学を理解できないと世界と互角に渡り合えないとの考えもあるようです。データ社会への変化を勘案すると妥当な方向性なのではないでしょうか。
企業に目を移すと、勤続30年の前職でもデータを重要視する動きが年々加速していきました。議論の場ではデータ・ドリブン、エビデンス・ベースなどの用語が頻繁に用いられるようになりました。特に最後の10年ほどは著しかったように思います。その間、世間ではデータを重視するような変化をあまり感じませんでしたが、コロナ禍で一挙に加速して「データ」「エビデンス」などの言葉が飛び交うのを目の当たりにし、データ社会の始まりを見たような感覚を抱いたことを鮮明に覚えています。
このように考えてみると、文系に進んだとしても数学を回避していくことは近視眼的にはメリットがあるかもしれませんが、長期的視点に立つと不利益を被るかも知れません。受験科目として採択するかは別として、学生のうちにできる限り数学を学んで欲しいと思います。
それでは数学を学ぶことの重要性にはどのようなものがあるのでしょうか?私の経験からではありますが、いくつか挙げてみたいと思います。
論理的思考力の向上
まずは論理的思考力が向上することが挙げられます。計算問題ひとつとっても、筋道を立てて解いて行く必要があります。文章題であったり、関数や図形問題、さらには証明問題となると筋道を立てることの重要性がさらに増します。この筋道を立てることが論理的に思考することになります。
このように論理的に考えることは問題を解決するのにも役に立ちます。問題解決力などといわれるものです。社会に出ると解決できない問題や課題がたくさんあります。それらをどうやって解決するのか、筋道を立てて考える必要があります。ひとつの方向性で解決できないことも多々あります。このようなときは何が問題だったのか、別の方策はないかと、ここでも論理的に考える必要が出てきます。論理的に考えることですべてが解決する訳ではありませんが、問題や課題に向き合う際に必要である力であることは確かです。
ものごとを俯瞰してみることができる
次に挙げられるものとして、ものごとを俯瞰してみることができるようになる、があります。数学の問題で、一目ですぐに解法の思いつかない問題に出会ったことがあるのではないでしょうか。このような問題を解くには、全体を俯瞰し、筋道を立てながら進めることになります。途中でうまくいかないと分かると、どこがおかしいのか、全体を俯瞰しながら筋道を立て直します。このようなことを繰り返して解き進めることになります。
数学の問題を例にしましたが、社会で目にする問題や課題を解決しようとすると、このようなステップを踏まざるを得ません。このとき、全体像を見つめ直す、つまり俯瞰してみることが大切になります。
さらに俯瞰的にみることで、ものごとを概念化したり抽象的にみることができるようになります。このような見方は創造力に結び付く可能性があり、今後必要とされる力となり得ます。
考え抜く力がつく
もう一つ、考え抜く力がつく、ことが挙げられます。途中で諦めてしまっては元も子もありませんが、諦めずに取り組むことで考え抜く力が身に着きます。分からない数学の問題に出会ったとき、すぐに解答を参照することも受験のテクニックとしては必要かもしれませんが、最後まで考え抜いてみることで景色が一変することがよくあります。教科書やネット情報などを調べてながらでも結構です。自分の頭で考え抜いてみることが大切です。
大学で自然科学系の講義を受け持っていますが、学生にこの考え抜く力を身につけて欲しいと常に訴えています。様々なテクノロジーが台頭する世の中では、ものごとの進みが益々加速する方向にあります。何が正しくて、何が正しくないのか、益々不透明になってくるのではないでしょうか。AIやChat-GPTなど便利なテクノロジーの汎用性が高まってきていますが、使い方を間違えると我々の思考を委ねてしまうことになりかねません。今後、一人ひとりがとことん考え抜く、つまり自分の頭で考えることが益々重要になってくると思います。
最後に
文理選択を否定する意見がありますが、目の前にある文理選択は避けて通ることができません。そのため、多くの学生は文系・理系のどちらかに進む選択をしなければなりません。文系・理系どちらに進んでもいいと思います。しかしこの選択を機に数学を学ぶことを避けないようにしてもらえればうれしく思います。数学的な考え方を少しでも身につけておくことは皆さんの将来にプラスになることはあってもマイナスになることはありませんので。